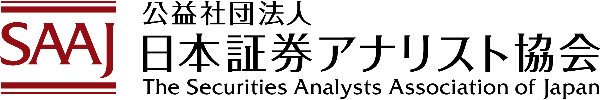
イベントトップに戻る
インタビュー要旨

【Q1:現在のお仕事内容をお聞かせください】
債券系マルチアセットのクオンツ・ポートフォリオ・マネジャーとして、運用モデルの研究開発や、実際のファンドの運用を行っています。具体的には、ファンドのモデルポートフォリオを策定したり、運用戦略を実装したり、売買計画を立てた上でトレーダーに発注を出したりといった業務です。また、自身の出身である京都大学の経営管理大学院で非常勤講師も兼務しております。
運用戦略が実際のファンドになるまで
各会社によるところもあると思いますが、新規でファンドを組成する際、ポートフォリオ・マネジャーが個別に自分の得意とする運用戦略を提案、あるいはチームで様々な戦略を組み込んだ運用を提案し、シードマネーと言われる自社の自己資金でインキュベーション・ファンドとして、運用を開始します。提案した運用戦略の実装結果、いわば“種まき”した結果で、運用がうまくいっているものが本当にファンドとして日の目を見る、という感じです。またはお客様からの、こういったファンドがほしいといったニーズを元にご提供することもあります。
【Q2:これまでの吉田さんのキャリアの変遷をお聞かせください】
証券会社で金利リスク管理、銀行でM&A業務、投資顧問で債券FM
大学院修了後新卒で大手の証券会社に就職し、リスク管理部で金利リスクの管理担当となったことが、私のキャリアのスタートになりました。その後親会社の銀行に出向してM&Aの担当となり、財務のモデリングを構築したり、顧客となる企業さんへの対応をしたりといった営業的要素もある業務となりました。しかし、もともとマーケットに近い仕事をしたいという思いでこの業界に入ったこともあり、ちょうどある投資顧問会社が債券ファンドマネージャーを募集していたので自身のやりたいことを優先したいと考え応募し、転職いたしました。
毎週末京都に通い、博士号を取得
債券ファンドマネージャーとしての日々を送るうちに、より深く債券市場について研究したいという思いが強まり所属先とも相談の結果、土日のみ社会人向けに開講する大学院の博士課程に進学することになりました。
モチベーションの維持に苦心
休職することなく進学できたのはいいのですが、毎週末、京都に通うこととなり体力的にもきつかったですが、もっと大変なことはモチベーションの維持でした。コースワーク+修士論文の研究を行う修士とは違って、博士課程でしたのでリサーチがメインとなり、論文にまとめ上げねばなりません。いかに自分で研究を進めるか、また研究を進めるだけではなく発表などで成果も求められるハードな日々を過ごしましたが、無事3年間で博士号を取得しました。
市場環境の変化をとらえ、マルチアセットPMへ
博士号を取得した2020年初めの債券市場は、各国とも超低利環境でした。利回りが取れない環境下で、将来的に金融政策が正常化していく過程に入っていけば、債券運用を取り巻く環境はより厳しくなると考えていました。そこで、専門としていた債券から、投資対象となるアセットクラスをより広げたいと考え、現在所属する会社でマルチアセットのポートフォリオ・マネジャーとなり、現在に至っております。
【Q3:吉田さんは理系大学院ご出身ですが、なぜ証券会社といった文系就職をされたのでしょうか?】
理系でも金融機関やコンサルへの就職は珍しくない
理系でも、いわゆるサイエンスを扱う理学系とテクノロジーを扱う工学系の2種類あり、工学系の学生は実学につながる学習や研究を行っているので、専門性を活かせるメーカーやIT系に就職するケースが多い印象です。一方で理学系では、例えば私の専攻では3割程度が研究を継続し、あとは公務員が多く、民間に就職する学生の行先ではメーカー以外にもコンサルや金融がそれなりにいましたので、金融業界が文系就職という意識はなかったです。金融業界に就職した先輩後輩の話を聞いても、デリバティブのモデル開発やポートフォリオ最適化の話などを聞き、理系が活躍できるフィールドがあると感じておりました。専門分野が異なって直接的に活かせなかったとしても、自分の中ではすごく良い選択をしたと思っています。
【Q4:CMAとしての強みは】
体系的に学べる、転職先の応募条件であることも
理系出身なので金融経済というのを体系的に学ぶ機会がなかったため、それを実務に使える形で学べるたことはメリットだと思います。強みとしては、やはり転職の際に、私のようないわゆるフロントの職種を志望する際には、応募条件に入っていたりするので、今後フロント業務に就きたい方なら、取得しておいた方がいいかもしれません。
【Q5:吉田さんの夢をお聞かせください】
実務と研究者の橋渡し役に
これまで実務に携わりながら、博士号を取って研究を行ってきましたので、両方がわかる人材になりたいです。問題意識としては、実務家と研究者がコラボレーションする場面は多い中で、お互い文化も立場も違い相互理解が難しい局面に、自分のような両方の側面に通じている人材が触媒となって、双方をつなげる役割を果たしたいと思っています。具体的には、大学の先生と共同研究を行っている中で、日本株市場のモメンタムの測定方法の問題点や、債券投資家予想の上方バイアスなど、まだまだ解明したい点がたくさんあり、興味は尽きないです。
【Q6:みなさんへのメッセージ】
前例にとらわれない、キャリアの分散
前例にとらわれないでチャレンジすることが大事だと思っています。私も、社会人になってわざわざ京都まで行って博士になってどうなるんだと言われたりもしましたが、チャレンジしたいことがあれば、先に手掛けた方が、先行者利益が取れると思います。もう一つは、証券アナリスト的に言うとキャリア形成においても分散効果は大事だと思っています。環境が激変している中で、一つの会社に定年まで勤めて行く方法もありますが、リスク分散をしながらキャリアを築いていく方法もあり、そのことで今までは見えてこなかった別の可能性が見えてくるかもしれません。私もこれからももっとチャレンジしたいので、みなさんと一緒にやれたらいいなと思っています。
